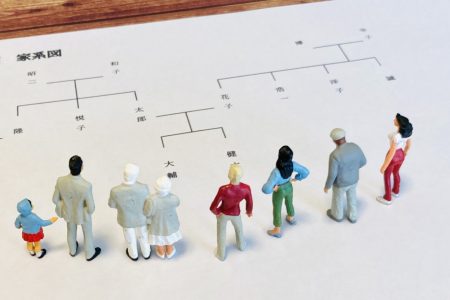「せっかく遺言書を書いても、きちんと保管しなければ無効になってしまうかもしれない」
――そう聞いたら不安になりませんか?
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの種類があり、それぞれ保管場所や方法に大きな違いがあります。
特に、自宅保管と法務局での保管、公正証書の保管には注意点があり、正しく理解することが大切です。
この記事では、遺言書の保管方法と注意点をわかりやすく解説します。
1.遺言書の保管が重要な理由
1-1 保管方法によって効力に影響はあるのか
遺言書は、書いただけでは意味をなしません。
残された家族に確実に見つけてもらい、正式な手続きを経て執行されることで初めて効力を持ちます。
そのため、「どこに保管するか」「誰が把握しているか」はとても重要です。
1-2 遺言書が見つからない・無効になるリスク
自宅で保管していた場合、
「存在自体が気づかれない」「破損や紛失」「改ざんの疑い」などのリスクがあります。
発見されても形式不備で無効になることも少なくありません。
保管方法次第で、せっかくの遺言書が役立たない可能性があることを意識しましょう。
2.自筆証書遺言の保管方法
2-1 自宅で保管する場合のメリット・デメリット
自宅で保管する最大のメリットは手軽さと費用がかからないことです。
書いたそのままを封筒に入れて金庫などに保管すれば完了します。
ただし、紛失・発見されない・改ざんの疑いをかけられるリスクが大きく、家庭裁判所での検認手続きも必要になります。
2-2 法務局での保管制度を利用するメリット
2020年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を使えば、法務局で安全に保管できます。
主なメリットは以下の通りです:
- 紛失や改ざんの心配がない
- 検認手続きが不要になる
- 家族がすぐに存在を確認できる
費用は1件3,900円と負担も少なく、自筆証書遺言を書くなら法務局での保管を強くおすすめします。
3.公正証書遺言の保管方法
3-1 公証役場での保管と家族への伝わりやすさ
公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場で原本を保管します。
原本が確実に保存されるため、「見つからない」「無効になる」といったリスクがほぼありません。
家族も必要に応じて遺言検索システムで確認でき、スムーズに手続きへ進めます。
3-2 費用や手間を含めたデメリット
公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いや手数料が必要で、費用は財産額によって数万円~十数万円かかります。
手間と費用はかかりますが、確実で安心な遺言の残し方と言えます。
4.遺言書保管でよくあるトラブル
4-1 自筆証書遺言で発生しやすいケース
- 遺言が見つからなかった
- 書き方の不備で無効になった
- 改ざんを疑われて家族間で争いになった
こうしたトラブルは、自宅保管の自筆証書遺言で特に多く発生しています。
4-2 公正証書遺言でも注意すべき点
公正証書遺言でも、内容が古いまま更新されないとトラブルになります。
例えば「相続人の状況が変わった」「財産が変動した」ときなど、定期的に見直すことが大切です。
5.安心のために今からできる準備
5-1 遺言書を確実に残すためのチェックポイント
- 自筆証書なら法務局保管を選ぶ
- 公正証書なら定期的に見直す
- 保管場所と存在を信頼できる人に伝えておく
これらを実行することで、「遺言はあるのに使えない」という事態を防げます。
5-2 専門家への相談・活用のすすめ
遺言は法律の知識が必要になる場面も多く、専門家に相談することで安心感が大きく変わります。
行政書士や司法書士などに依頼すれば、作成から保管方法のアドバイスまで一貫してサポートを受けられます。
◆まずは無料相談・セミナーで学びませんか?
遺言書の作成や保管は「いつかやろう」と思っているうちに後回しになりがちです。
ですが、元気な今だからこそ、家族のために準備できることがあります。
当センターでは、遺言・相続に関する無料相談を随時受け付けております。
「自宅保管と法務局保管、どちらがいい?」「公正証書にすべき?」といった疑問にも、専門家が丁寧にお答えします。
▼【無料相談はこちら】
お問い合わせページへ
さらに、遺言や相続を基礎から学べるセミナーも定期的に開催中です。
「まずは話を聞いてから考えたい」という方にぴったりです。
▼【最新セミナー情報はこちら】
セミナーのお知らせページへ
大切な想いを、確実に家族へ残すために。
今できる第一歩を踏み出してみませんか?